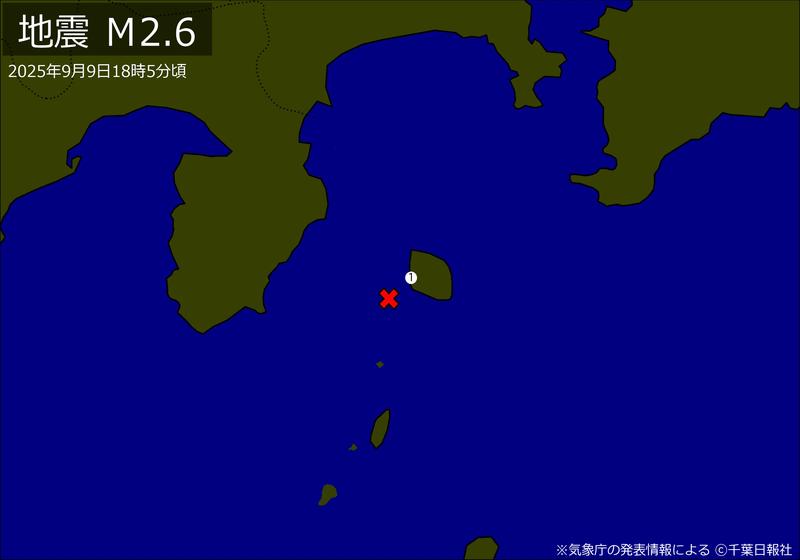オオガハスの実は1951年、花見川区の東京大学農学部厚生農場(現・東京大学検見川総合運動場)で、植物学者の大賀一郎博士(1883~1965年)らの発掘作業で見つかった。
第2次世界大戦当時、農場内では代替燃料として使用する泥炭を採掘していた。その際、丸木船とともに古代ハスの果托(かたく)が出土した。
ハスを研究していた大賀博士が果托出土の情報を知り、農場へ種の発掘を要望。1951年3月3日、農場管理人の呼び掛けで集まった地元の小中学生や住人、企業らが協力して作業が始まった。
成果もなく迎えた同月30日、現・市立花園中学校の女子生徒が古代ハスの種1粒を発見。その後、2粒が見つかった。大賀博士の自宅で発芽処理を開始。3月30日に出土した1粒だけが順調に生育した。
翌52年、同農場と千葉公園、県農業試験場へ分根。同農場で飼育される牛馬による食害を防ぐため、近くに住む農業委員に栽培を委託した。この1株が7月1日に最初のつぼみを付け、同18日に開花した。
古代ハスは、大賀博士にちなんでオオガハスと名付けられた。偉業は新聞や雑誌で広く発信され、米国の写真雑誌LIFEで公開されると大きな反響を呼んだ。
オオガハスは54年、千葉県の天然記念物「検見川の大賀蓮(はす)」に指定された。実と同じ地層から出土した丸木舟の放射性炭素年代測定の結果に基づき約2千年前のものと推定された。
千葉公園や東京大学旧緑地植物実験所では、オオガハスの系統保存に取り組んでいる。交雑した種子での繁殖を防ぐため、開花後の果托を確実に刈り取り、蓮根による繁殖で系統保存をしている。
県民の日は開花シーズン。今年も2千年前に千葉市内を彩った大輪が咲き誇り、県の誕生日を祝う。