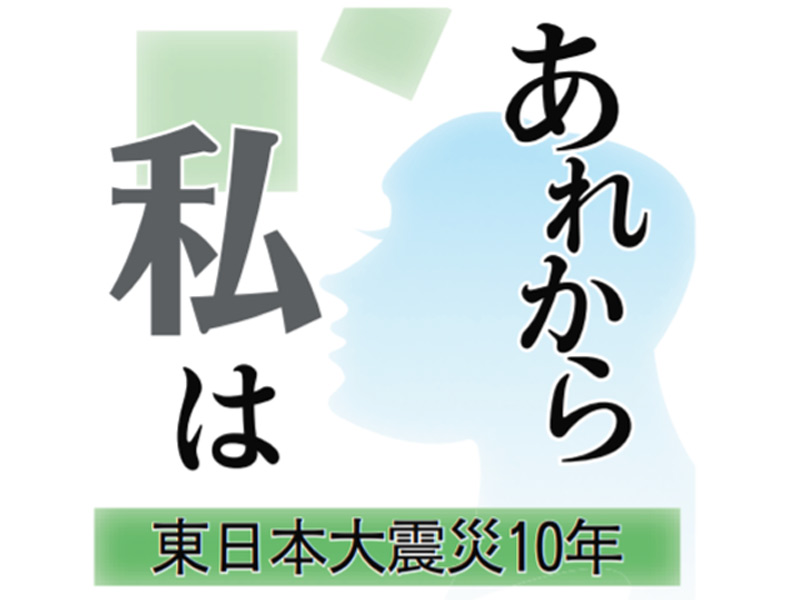
日本有数の巨大テーマパーク、千葉県浦安市の東京ディズニーリゾート。その従業員らが東日本大震災の日にとった行動が、後に「神対応」として称賛された。来園者の頭を守るため売り物のぬいぐるみを配ったり、シャンデリアの妖精を演じてゲストを安全な場所へ誘導したり。中でも有名なエピソードが、普段は決して見せてはならない「バックヤード(舞台裏)を通る1500人の避難計画」だった。あれから10年。その決断を下した担当者は異動を経て再び震災当時と同じ部署に配属されていた。彼が今語るのは「あの対応に間違いはなかった」という確かな自信と、10年前もこの先も変わらない「ゲスト(来園者)の安全最優先」というオリエンタルランドの信念だった。
(デジタル編集部・山崎恵)
 コロナ禍で人数制限しながら運営を続ける東京ディズニーランド=2020年10月
コロナ禍で人数制限しながら運営を続ける東京ディズニーランド=2020年10月
まだ肌寒さの残る2011年3月11日。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーは春休み中の大学生や家族連れらでにぎわっていた。来園者は合わせて7万人。ちょうどディズニーシーで屋外ショーが始まったころ、激しい揺れが襲った。
「これはパークが大変なことになるんじゃないか」
ディズニーシーの運営責任者だった田村圭司さん(53)の脳裏には、地震の恐怖よりも先に来園者や従業員の姿が浮かんだ。すぐに緊急時の無線基地局となるセキュリティ棟へ急ぎ、けが人や建物の損壊についての情報を集めた。同時に、パークでの災害対応の基準が最高レベルの「ステージ3」に決定した。
主にアトラクションの運転を中断する「ステージ2」までとは違い、ステージ3では来園者・従業員の全員を屋外に退避させ、建物に二次避難させるという大きなミッションが課せられる。
「あまり公表していませんが、当時のパークの震度自体はぎりぎりステージ2のレベルだった。しかし誰もが尋常じゃない揺れだと判断し、ステージ3の発令が決まったんです」
訓練は何度も繰り返してきたが、ステージ3の発令は初。一抹の不安もよぎった。
ランドからシーへ 1500人の大移動
 東京ディズニーシーのシンボル、プロメテウス火山=オリエンタルランド提供
東京ディズニーシーのシンボル、プロメテウス火山=オリエンタルランド提供
パークでは、キャストが来園者の不安を取り除こうと「この建物は安全です」と一人一人への声掛けに徹したこともあり、屋外退避で大きな混乱は起きなかった。ただ問題はその後。来園者を建物に二次避難させるための安全確認に想像以上に時間を要した。当時は今に比べて安全診断を行えるスタッフの数や点検ルートが十分ではなかったためだ。
徐々に日が暮れ気温は下がり、雨も降ってきた。ディズニーシーで二次避難の指揮をとっていた田村さんに、オリエンタルランドの災害統括本部から電話がかかってきた。「ランドで屋内に入れないお客さまが2千人ほどいる。シーに収容できるか」。
田村さんはすぐさま自転車でシーの建物を見て回った。ショップ、レストラン、劇場…正直全員を収容できるかどうかは分からなかったが、決意も込めて答えた。「大丈夫、いけます」。その一言で、ランドからシーへの大移動が決定した。
ただ、ランドとシーは背中合わせに立地しており、ランドの正面玄関から出てシーへ移動すると約30分もの道のりを歩かなければならなかった。外は暗く、浦安市を襲った液状化現象で道はガタガタと隆起していた。来園者の中には子ども連れも、ベビーカーの人も、お年寄りもいた。そんな危険な道を歩かせるわけにはいかない。田村さんはみじんの迷いもなく提案した。「パークの裏道を通ればすぐだ。バックヤードを通ってもらいましょう」< ・・・
【残り 4087文字】







